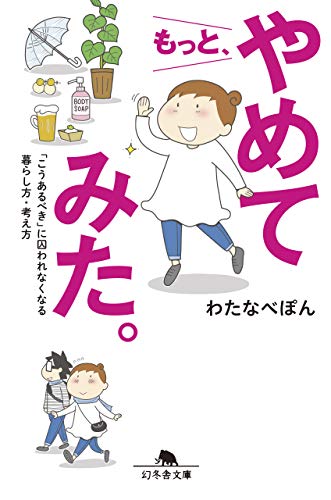「料理をやめてみた」
誰かの「やめた」ことに焦点を当てるシリーズ企画「わたしがやめたこと」。今回は、エッセイストの能町みね子さんに寄稿いただきました。
能町さんがやめてみたのは「料理を作ること」。
料理が苦手だったにもかかわらず、長年「きちんと自炊をしなきゃ」という“常識”にとらわれ、結果「自炊すら満足にできない自分」への“落胆”につながっていたそう。
自炊が出来ると褒められるし(特に独身男性)、手間暇かけて作った手料理を家族に出すお母さんが理想という価値観が根強く残っているのは間違いありません。
外食は栄養が偏って不健康になりがちだし、節約にならない。自炊なら健康的で節約にも繋がる!というイメージもあります。
これは、にほんブログ村の「セミリタイア生活」や「節約・節約術」などのブログを読んでいても感じることです。
ただし料理ができる腕があってなんで、誰にでもできる(再現性のある)ことではありません。
「自炊は絶対的正義」という常識に逆らう
そういった世間の言葉によって、「自炊は絶対的正義」という常識に縛られていた能町みね子氏は料理を一切やめてしまったと。
たまにやる、ではなく一切やめるとは思い切った行動だと思いますが、調理器具を買わずに済むし置く場所も必要ないし、食材のゴミも減るし、ある種のミニマリストかな?
一人暮らしで自炊をするのは、家族の分をまとめて作るよりは効率(お金も時間も)が良くないし、いいんじゃないでしょうか。
子どもには手間暇かけて作ったものを毎日食べさせなければいけない、という呪縛にとらわれたお母さんも大変ですけどね。
冷凍食品を使うと「手抜き」か「手間抜き」か論争になったように。
「自分の快適さは自分にしか分からない」
何よりも「苦痛」と感じていたのなら続けられません。
「自分の快適さは自分にしか分からない」という言葉に集約されているように思います。一人暮らしならなおさら。
私にとっては「毎日働くのが苦痛だったからやめた」のが今のセミリタイア生活ですし、他人から退屈そうに見えても、自分にとっては快適。
一度やめたらもう二度とやってはいけないわけでもなく、またやりたくなったらやればいいだけですしね。