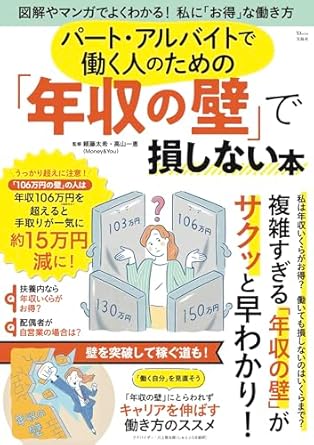「年収103万円の壁」はどこから来たのか
自民、公明、国民民主の3党は11日、2025年から「年収103万円の壁」を引き上げることで合意した。エコノミストの崔真淑さんは「103万円の金額が制定されたのは1995年のこと。消費者物価指数は当時から上昇しているのに、この基準が据え置かれたままの現状だった」という――。
課税最低ラインの103万円の引き上げを巡る議論の中では、国民民主党の主張する最低賃金の上昇率で考えるのか、あるいは消費者物価指数で考えるのか、様々な指標が取り沙汰されたようです。
いずれにせよ30年前のままというのはおかしな話なのですが、上げ幅についてはまだ確定していません。
「カロリーベース」で考えると
記事で気になったのは、103万円の壁が「カロリーベース」から算出されたという点です。
おそらく、最低生活費という意味であり、それは基礎控除(48万円・2019年までは38万円)の算出根拠だと推察されます。配偶者控除・扶養控除は38万円です。
食費については、一人最低いくらかかるという計算しやすいし、生きていくために絶対に必要な金額が算出しやすい。
年間38万円なら月約3.17万円です。1人あたりの食費と考えると世間一般の平均に近い数字かと。
そして昨今の食品価格の高騰を考えれば、これを上げないとおかしい。
安定していた主食のコメの価格が急上昇・高止まりしていることを考えると、2割くらい増やしてもいいのでは。
それでも基礎控除で10万円くらいのアップにとどまるわけですけどね。
基礎控除引き上げが「お金持ち優遇」と言うならば
基礎控除の引き上げについては、所得が多いほど(適用最高税率が高くなるほど)減税額が増えるため、「お金持ち優遇」という反対意見も聞かれます。
しかし基礎控除は合計所得金額2400万円以上から減らされ、2500万円以上ならゼロになる仕組みが2018年の税制改正で導入されています。
この年収額による基礎控除低減をもっと引き下げてしまえば、お金持ち優遇の度合いを減らすことが可能なんですよね。
簡単に言えば、基礎控除の引き上げは合計所得金額が800万円以下という条件をつけるとかです。
なんなら給与所得控除額のテーブルもいじってしまえば、税収減を少なくできます。
結局は高所得者の増税になるから、それを嫌がる人の抵抗もあるのでしょうけどね…