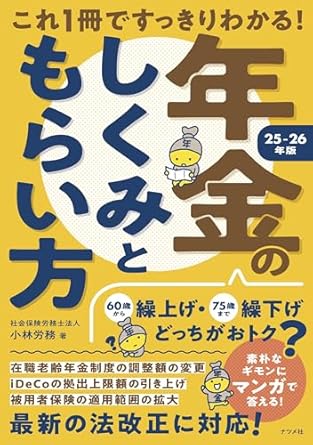年金制度の現実を語る
基礎年金(国民年金)の元を取るには約10年、厚生年金は会社負担分まで含めて考えると20年かかってしまう。
だから平均寿命を考えると「ほとんどの人は元を取れずに損をする」という話をされています。
「ほとんど」というと、8割くらいの人が損をするイメージなのでちょっと大げさに感じますね。
年金を含む保険というのは統計的なデータを基に平均的な寿命で死ぬ人が損も得もしない設定の基本であるため、「半数の人が損、半数の人が得」くらいに考えるのがいいかと。
しかし「人生100年時代」ですよ?
一方、金融機関やFPは「人生100年時代」で長生きの不安を煽って資産運用を勧めてくる時代です。
「老後2000万円問題」だって、95歳まで30年を生きる計算でされています。
半数が95歳まで生きるようになったなら、「ほとんど(半数以上)の人が得」になりそうです。
ただその時には年金支給額を抑えたり、年金支給開始年齢を遅らせたりする措置が取られる覚悟をしておいた方がいいかもしれません。
自分が平均寿命付近で死ぬと考えるのか、100歳近くまで生きると考えるかで損得の計算も、老後のためにどう備えるかも変わってきます。
妻が専業主婦の家庭は
寿命で損得が出てしまう以上、平均寿命(余命)が短い男性は損する人が多く、長い女性は得する人が多くなります。
サラリーマンの夫と専業主婦の妻の夫婦で考えると、夫が早々に亡くなって妻が自分の基礎年金と夫の遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)を受け取れます。
それで妻が長生きすれば元を取れてしまいます。
遺族厚生年金については、所得税が非課税であり、医療保険の所得割額の算定にも入りません。
国民年金の第3号被保険者となる専業主婦(主夫)は、この点でもおトク感がありますねぇ。
第3号を廃止するよりも、遺族厚生年金を課税対象にする制度変更の方がやりやすいかもしれません。
もちろん国がやろうとしたら「高齢者イジメだ!」と大騒ぎになることは必定ですけれど…